冬は乾燥の時期ですから、加湿器を使って室内の空気を加湿しましょう。
あれは本当なんでしょうか?
夜寝る時も、喉が乾燥で痛くなるから加湿器使って加湿してる人いませんか?
ちなみに我が家には加湿器はありません。
特に暖房を消した後に関しては除湿機の使用をおすすめします。
結露で悩んでる人は特に続きを読んでみてください。
冬の結露と湿度の関係
まずは結露と湿度の関係から見ていきたいと思いますが、手っ取り早いので、まずはこの表を見てください。※後で使う数字は黄色でマークしてます
| 気温(℃) | 飽和水蒸気量(g/m3) |
|---|---|
| 30 | 39.6 |
| 25 | 30.3 |
| 20 | 23.0 |
| 15 | 17.2 |
| 10 | 9.4 |
| 5 | 6.8 |
| 0 | 4.8 |
| -5 | 3.2 |
| -10 | 2.1 |
多分、飽和水蒸気量という言葉は中学だか高校だかで出てきてると思います。
気温が何度の時に、1立方メートル(以下1m3と表記します)の空気中にどれだけの水蒸気が含むことができるかという最大の数値を表したものです。
そもそも湿度(%)と言うのは、
で表され、上の表の右の数値が分母に入ってきます。
これでいくと、25度の時に大気中に含まれる水蒸気の量が30.3gあれば、30.3/30.3=1となり、湿度100%と言う事になりますし、大気中の水蒸気量が20.2gとなると20.2/30.3=0.67となり67%くらいと言う事になります。
室内環境に必要な湿度
大体一般的には40%~60%と言われるそうです。
意外と低いんですね。
上記の例であげた25度の時であれば15g前後ということです。
暖房をした室内に、なぜ加湿が必要になるのか

加湿が必要な理由は、空気が乾燥するからに他なりません。
じゃあ、加湿器で・・・というのは少し待っていただいて、どれだけ加湿が必要なのかを考えて使みたいと思います。
※なお、湿度が室内に一定に広がるといったいくつかの理想的な諸条件は重なります。
加湿が必要な時
これは間違いなく暖房を使用して室温を上げる時です。
仮に、湿度60%、10度の室内を暖房して、大気の水蒸気量を変えずに室温だけ25度まで暖房すると湿度はどうなるのでしょうか。
上の表の左を参考にして、10度、湿度60%とすると1m3あたりには5.6gの水蒸気が含まれている状態となります。
| 暖房前 | 暖房後 | |
|---|---|---|
| 室温 | 10 | 25 |
| 水蒸気量 | 5.6 | 5.6 (※1) |
| 飽和水蒸気量 | 9.4 | 30.3 |
| 湿度 | 60 | 18.5 |
計算式の分子に当たる水蒸気量が変わらず、分母が大きくなりますから、数値は小さくなり湿度18.5%となります。
やはり乾燥してますね。
じゃあこれを湿度60%まで加湿しようとすると
必要な水蒸気量(※1)をXとして計算
60%=X/30.3*100
となり、X=18.2となります。
元の水蒸気量5.6gを引くと、12.6g程度の加湿が必要という計算になります。
もちろんこれは1m3あたりの数字ですけど。
加湿量
暖房時に加湿したほうが良い事がわかりました。
※1g=1cc=1mlとなります
じゃあどれくらいの加湿すればいいのかといいますと、ご自宅の部屋の大きさにもよりますが、6畳間(約10㎡とします)天井高2.4mで多くても約24m3の空間となります。
20畳のリビングですと80m3位になります。
単純に上の例でいきますと、6畳間で12.6×24=302g(ml)、20畳でも12.6×80=1,008g(ml)程度の加湿でいいんです。
意外と少ないと思いませんか?
1000mlというと牛乳パック1つになるから多いですか?
加湿器の性能
じゃあ実際の加湿器でどの程度加湿出来るんでしょうか?
パナソニックのヒーターレス気化式加湿器FE-KXP07のスペックをお借ります。
| お急ぎ | 800ml |
|---|---|
| 強 | 700ml |
| 中 | 500ml |
| 弱 | 330ml |
| 静か | 150ml |
となっています。
20畳の部屋でも約1008mlの加湿で済むはずですから、まあ数時間使用するには適した数字なんでしょうかね。
ちなみにこの商品の加湿器の水タンクは4.2リットルあります。
生活するうえで発生する水蒸気

マスクをしていて眼鏡が曇った経験がある人もいらっしゃる通り、人間はじっとしていても水蒸気を発散しますし、人が生活する上で様々な水蒸気というものは発生しています。
調理などによる加湿
冬は鍋物が恋しくなりますよね。
でもあれって最後になると鍋の中の出汁だったりお湯だったりって蒸発して、とても少なくなりますよね。
料理をされる方なら、調理している鍋の蓋をあけたときの、蓋からこぼれる水の量を想像しやすいと思います。
部屋干しによる水蒸気の発生
また冬場は洗濯物が乾かず、室内に干している方もいらっしゃるでしょうし、朝は忙しいからと夜洗濯物を干して寝る方もいると思います。
乾いたタオルと脱水が終わったタオルの重さを比較しても、洗濯物に含まれる水の量というのは想像できるでしょうけど、それだけの水分が室内の空気の中に放出されているんですよ。
▽ちなみに冬場の洗濯ものにはサーキュレーターを併用すると驚くほど早く乾きます。

石油ファンヒーターは結露の対策が必須
ファンヒーターをはじめとして、昔ながらのストーブの上でやかんを掛けてお湯を沸かしてる人もいらっしゃると思いますけど、石油などの油からでる水蒸気というのは意外と水蒸気も発生させているのです。
実はこれらが意図的に加湿する必要がないくらいの数字なのですが、当然生活空間には衣服や寝具、ソファーだったりカーテン、カーペットが吸湿するということもありますし、人の出入りによって空気が換気されると言う事もありますから、これらの水蒸気はある程度相殺されるという前提で続きを書いてみたいと思います。
※生活空間のないオフィスとなると話が変わります
冬の結露対策に除湿機が必要な時
夜眠る時、エアコンやストーブをつけて寝られる人っていらっしゃいます?
ストーブはもちろんですけど、多分消して寝る人が多いんじゃないかと思います。
そうなると気温て下がりますよね?
暖房した時のシュミレーションを逆にしてみます。
暖房時25度湿度60%の室内を10度まで下げたとすると・・・
| 暖房時 | 暖房消した後 | |
|---|---|---|
| 気温 | 25 | 10 |
| 水蒸気量 | 18.2 | 9.4(-8.8) |
| 飽和水蒸気量 | 30.3 | 9.4 |
| 湿度 | 60 | 100 |
気温が下がると空気に含むことができる水蒸気量が少なくなりますから、湿度100%となっても8.8gもの水蒸気が残ってしまうんですね。
じゃあ、この8.8gがどうなるの?というと、それが結露という形で現れてくるわけです。
もちろん1m3当たりですから、上記で例にした6畳間ですと211g、20畳間ですと704gもの水蒸気が結露として窓やヒートブリッジ(熱橋)と呼ばれる部屋の隅部で発生することになります。
なので、眠ってる時に加湿器なんか掛けても大気中の水分量は増えず、結露を増やすだけで何の効果もないんですよ。
あえて言うならば、空気中の水分量が少ないことには違いありませんから、気になれば枕元に濡れたタオルでも干しておけば十分だと思いますね。
冬に必要なのは加湿ではなく、調湿なのです。
暖房時は加湿、暖房を消した時には除湿という二つの作業が必要というわけです。
ちなみに我が家では夜中に洗濯物を干してその下でほぼ毎日除湿機が稼動しています。
洗濯物が水分を発散できるように乾燥空気を送ってやるので、よく乾くんですよ。
なぜ冬は加湿器という常識が芽生えたのか
それは暖房器具がエアコンに変わったからです。
本来石油ストーブだったころにはタダでさえ水蒸気を発生させる暖房器具にやかんを掛けてお湯を沸かしていたご家庭も多かったと思いますから、特に意識することはなかったんですけど、空気を汚さないエアコンが主流になり始めてからは確かに加湿を必要になったという事実は間違いありません。
あとはビニールクロスなどの普及による調湿建材の減少などもあるかもしれません。
もう一つには冬になれば加湿器が売りやすいというメーカーの思惑というものもあるでしょうね。
まとめ
以前メンテナンスでお邪魔したお宅で、ファンヒーターで暖房をして、加湿器を使用した室内で洗濯物を干している割には「結露がひどい」と言われたお客さんがいらっしゃったのですね。
なので、せめて加湿器を止めてもらう事をお願いして帰りました。
最近は鉄筋コンクリートなどのマンションを始め、木造住宅でも高気密住宅が主流となってます。
そのおかげで、室内の空気は入れ替わりにくくなっていますので、上手に換気や調湿を利用して快適な住環境を作ってほしいと思います。
ちなみに我が家ではエコカラットをDIYしたところ、結構な効果があり驚いています。
▽関連ブログに飛びます
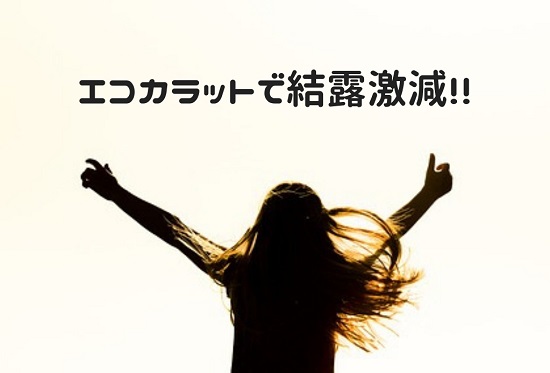
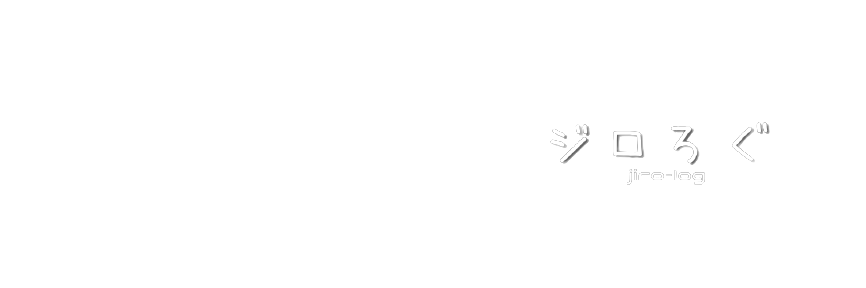




コメント