衣食住の中でも大きなウエイトを占める住宅費。
じつは先日我が家のウォークインクローゼットのなかにゴキブリが入っていくのを見かけました。
あかちゃばね
きちゃばね
あおちゃばね
…
テンション落ちた(T_T)— ジロ@Jiroの端株投資奮闘記 (@JIRO_invest) 2017年9月14日
なので、休みを使ってウォークインクローゼットを徹底的に片付けました。
他に隠れた連中はおらず、単独であった事も判明してやれやれ一安心でしたが、出てきたゴミの山を見て住居費について、ふと感じることがあったので記事にしてみました。
断捨離

最近断捨離とかミニマリストといった言葉があるように、最低限のものしか持たないという人達が増えてるみたいです。
どちらの言葉も最近いろんなところでチョコチョコ言葉は飛び交ってますからご存知の方も多いことでしょう。
クラターコンサルタント やましたひでこさんの提唱した断捨離は、ヨガの教えによるものを片付け術に落とし込んだとのことですが、実は私にとってそんな事は綺麗ごとであって、いらないものは捨てる。私にとってはこれがすべてです。
捨てる事が好きな夫に、捨てる事が苦手な妻
まさに我が家のことです。
私は一度捨てだすと、物が減るということに快感を覚え捨てまくります。「不要なもの、使ってないものを捨てた途端に入用になった」という事は誰しも経験する事ですが、それはタダの偶然と思うようにしています。
一方妻はそれが出来ず、誰かにあげたらいい、これは売ればいい・・・なんてやってる間に物は貯まる一方です。そのうち、あるはずの物がどこにあるかわからず買う。
結局この事を出費の面で考えると、捨てた直後に必要になったケースと同じなわけです。
子供服は捨てられない?

実はこの件に関しては私は妻に強要はしていません。一時期は強要をした時期もあるのですが、やはり母親として思い入れのあるものですし、何より逆効果です。
もっとも子供服に思い入れのあるのは私も同じですが、長年収納ケースに入れられたそれらは、自然と黄ばんだり、色褪せたり、虫が食ってたりして痛んできます。
なので、迷ってるな?と思ったらそっと「思い入れのあるものが痛んでいくのを見るのも嫌だよね」と暗に促してみます。そうすると意外とスッと捨ててくれるんですね。
もちろん保留しても強要はしません。
捨てると住居費が安くなる?
持ち家の場合
結論からいいますと、この1年で我が家から出たごみは、2tトラック2台から3台分くらいのゴミが出てます。大半は子供服だったりするのですけど、とにかくものすごい量です。
なぜそんなにゴミになったかというと、家を新築する際に物があふれるのが嫌で、とにかく収納を多めに作った事につながるかと思います。
屋根裏部屋に関しては、12畳ほどもある収納スペースがありながら足の踏み場もないほどでしたが、一時期はあふれかえっていた子供服も捨て、すっかりスペースが余りまくってきました。昨日のウォークインクローゼットも同様です。
そうして考えると、収納スペースに関してもお金を支払って作ってるわけですから、新築時のコストというものに反映されてるわけです。
断捨離で賃貸はさらに効果がある

私は持ち家ですので、それだけの収納スペースを確保する事ができますが、賃貸であればさすがにそれだけのスペースを確保する事は困難です。
職業柄マンションのメンテナンスで入居者のお宅へお邪魔する事もありますが、「あ、その部屋は物置になってますから・・・」なんてケースもあります。
つまり、荷物さえなければもっと小さな間取りの部屋=家賃も安く済むという可能性も否定は出来ないかと思います。
医療費削減にも効果は波及するかも
掃除機をかけ、拭き掃除を済ませてすっかり綺麗になったクローゼットを見て感じました。
これでアレルギーの原因を減ったね。と。
我が家は私を含め・・・というより、妻以外はアレルギー持ちでして、そのたびに耳鼻科に通ったりしてそれぞれ治療費が掛かります。
一度アレルギーになったらそれが治癒する事はないとは思いますけど、改善側へは影響してくれるはずです。治療費への波及というにはちょっと道は遠いかもしれませんが、少なくとも衛生的な状況になった事実を考えれば決して言い過ぎではないかと思いますね。
まとめ
このことは、物が手元に来た時に分別せずに、とりあえず収納へという行為がこの結果に導いています。
今はとにかく物があふれており、現代人は物欲に支配されていると度々思います。人が持ってるから欲しいとか、見得のためだとか。それ自体が万人に悪い事とは思いませんけど、果たしてそれが自分にとって必要なものでしょうか?
昔の人は、「起きて半畳、寝て一畳」と言っていましたけど、今は逆にそのスペースすら物によって侵食されてる時代です。不要なものは処分する、好奇心では物を買わない。
せっかく片付いた我が家ですので、そういったことを心がけたいと思います。
冒頭紹介した節約記事のご紹介

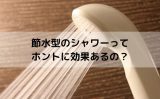
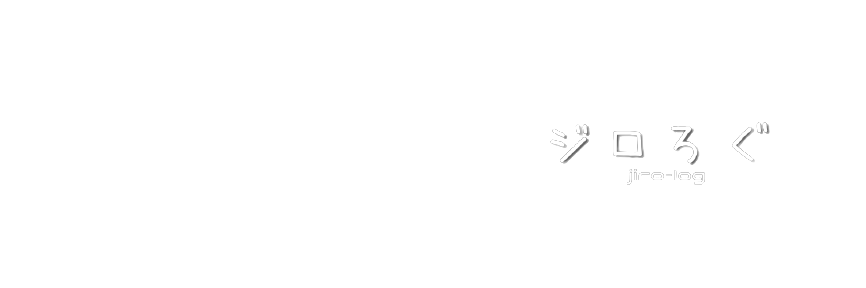




コメント