非常に経済が安定した時期が長く続いていますが、独立系投資ファンドなんかは暴落にそなえて現金比率を上げはじめたなんて言う話もチラホラ。
米株なんかは史上最高値の更新が続いてたりしますから高値圏で買うことに不安と感じる人も多いのかもしれませんけど、その一方で米国はバブルなんて言われて早何年か・・・。
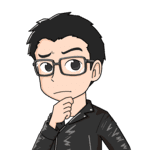
こんなときは、まだ上がることを信じて積み立てることしかできないのか??
でも、そんな経済が安定している今だからしておきたいのは暴落への備え。
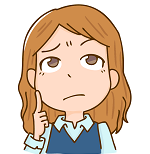
まさか、自分はこのまま暴落を経験せずに済むと考えている人もいないよね?
もちろん現金比率などを上げることも一つかもしれませんけど、こればかりはタイミングがわからない。
そこでこの経済が安定しているこの時に、暴落しても投資を続けていけるような環境というものを整えてみてはいかがでしょうか。
暴落時のメンタルを維持するためには脱ボッチ
話は変わりますが環境が変わったときどうしましたか?
進学、入学、社会人、転勤等々、誰しも身の回りの環境を変え今の生活を送っていると思います。
そんな時、身の回りに知り合いっていないとか、少ないっていう環境をどうしてきましたか?
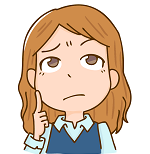
多分同じ境遇の友達を探したり、クラブや行事を通して友達を作ったりしてコミュニケーションの場を作ってきたように思う。
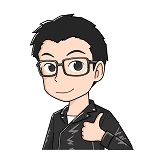
たぶん自分もそんな感じ。
なのでそのコミュニティに集まってみたらどうかな?というのが今回の話。
投資への理解者を増やす

投資について理解のある人がいますか?
ご夫婦であれば旦那さんや奥さん、独身であれば友人、会社の同僚、先輩後輩上司部下。
親兄弟だったり何かしらの理解をしてくれる人がそばにいますか?
こういう人がまわりにいらっしゃることは、以前も書いてますけど羨ましいことなんですよ。≫投資に関する家族の理解がある人がうらやましい
多くの場合、日本ではお金に関する話はタブーですから、仮にいたとしても黙ってるんですよね。
だから基本的に「投資をはじめたけど人に言えずに孤独」っていう人もいると思うんです。
私もそうでしたから。
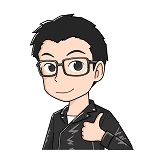
ちなみに今は妻も投資を始めてくれました^^
ブログでつながる

私はこのブログで投資やお金に関するテーマでこのブログを書いていますけど、お金に関することっていうのは王道というのはあっても正解はないと思ってるので、なるべく感じたことや感じてることなんかをリアルに書こうと思ってます。
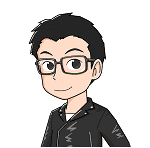
それは自分の不安は誰かの不安であったりもするだろうから。
自分自身、リーマンショック以降の経済が不安定な時に勇気づけられたブログというのはあるので、自分がそういう存在になれれば嬉しいです。
でも・・・
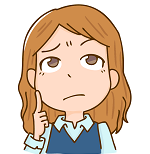
更新が途絶えてしまったブログがあるのも事実よね・・・。
やはり大きな損失を抱えてブログ更新というものは心理的に負担なのは理解できます。
ツイッターやSNSを利用する
実はブログで繋がるよりもっと手軽なのがツイッターなどのSNSを使った繋がり。
ツイッターをはじめとするSNSを介した犯罪というのはあちこちで起きていて、あまり良い印象を持っていなかったのですけど、ネット上とはいえブログ以上に同じ境遇の人とつながる事が可能です。
ブログだけではそのブロガーさんはどうしても表面的な存在なんですけど、リアルタイムでその人を感じる事でそのブログそのものも実在するものっていう認識ができた気がしたのを覚えています。
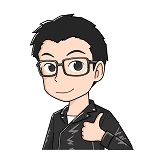
いろんな世代の人と繋がれるSNSって最高やね。
つながる相手は間違わないように
私もツイッターをはじめて4~5年ですけど、株価が順調な時には強気な発言してた割に、コロナショックなどで何度か暴落すると周りを巻き込んで売ってる人っているようです。
つい理論武装しているような人には引き付けられるものですけど、実際そういう人というのはあまりつながることをおすすめできないかな。
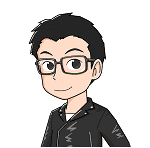
そこまで目の色変えてするもんじゃないでしょ?投資って。
投資だけでなく、いろんな実生活や考え方に共感できる人を探したほうがベターかと思います。
暴落した時に投資に対するメンタルを維持する方法
リーマンショックの頃に投資を始めたばかりだった私が一番不安だったのが、世界中で連鎖的に起きる経済危機、そして東日本大震災などの大不況。
「このまま投資をしていていいのだろうか」「投資をしているものはあっているのだろうか」という不安でした。
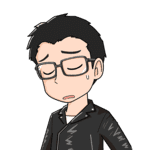
誰しも投資したお金が減っていくのが嬉しい人間はいませんから。
当時のわたしはブログしか知りませんでしたけど、そんなときでも定期的に投資信託を買い付けていた人もいたし、きっとツイッターの世界にもそういう人はいたはず。
投資に限らず何かを乗り越える時というのは、大抵誰かのサポートがあったことも多いんじゃないかと思います。
私もあの当時と比べるとリスク資産はかなり増えましたので、いざリーマンショック級の経済危機がきたときに乗り越えていけるのかどうかというのは不安な面もありますが、だからこそ私自身は「おはぎゃー」と言えるような人と繋がりたいと思ってます。
豆知識≫おはぎゃーとは
人は大なり小なり他人や環境に影響されるものですが、投資をするにあたっても周りの環境というのは自分の共感できる人たちと繋がっておいた方がよいのではないでしょうか。


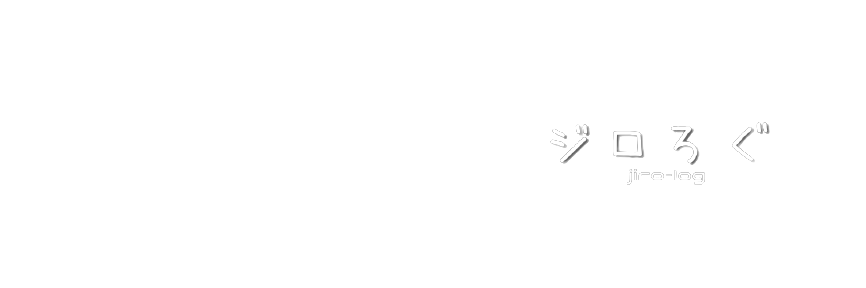
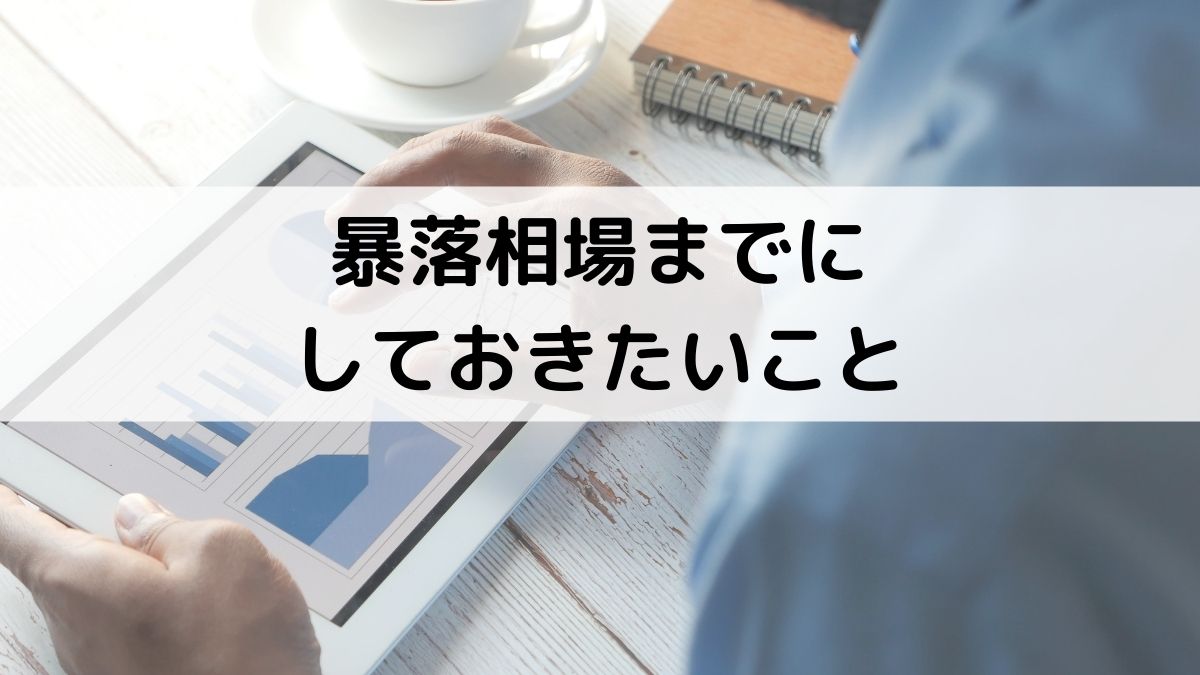

コメント